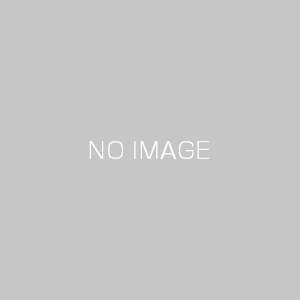魅力満載!パワースポット好き必見の櫛田神社
福岡市の中心部にある櫛田神社は、博多祇園山笠が奉納されていることで有名で、飾り山笠が6月を除き一年中展示されています。博多っ子からは「お櫛田さん」の愛称で親しまれています。古くより博多の総鎮守として崇敬を集めてきました。
櫛田神社はパワースポットと呼ばれる見どころがたくさんありますが、参拝の際に必ずしていただきたい5つのことがあるのをご存知でしょうか。これを櫛田神社へ行く前に知っておけばありがたみも増し、格段にパワーがアップすること間違いなしかもしれませんよ。
櫛田神社のご祭神・ご利益
御祭神は中殿に大幡主命(おおはたぬしのみこと)(櫛田宮)、右殿に須佐之男命(すさのおのみこと)(祇園宮)、左殿には天照大御神(あまてらすおおみかみ)(大神宮)をそれぞれお祀りしています。ご利益は、健康、不老長寿、商売繁盛などです。
櫛田神社の由来
櫛田神社は、博多の総氏神様としては最古の歴史を有します。ご祭神は伊勢国・松坂の櫛田神社より勧請した神大幡主大神(櫛田宮)で、奈良時代の757年(孝謙天皇天平宝字元年)に託宣によって鎮座されました。
八百万の神の最高神・天照大神(大神宮)と天照大御神の弟・須佐之男命(祇園宮)もお祀りされています。941年(天慶4年)藤原純友の乱の追討使小野好古は、戦勝奉賽のために須佐之男命を勧請したといわれています。
なお、天照大御神の奉祀についてはかなり古いこともあり、史実として不明とされています。 西暦757年の創建より1,260年以上にわたって、櫛田神社は総鎮守として博多の街を見守り続けてきました。そんな櫛田神社は、今日でも地域の人々から「お櫛田さん」の愛称で親しまれています。
櫛田神社の5つのパワースポット
櫛田神社を訪れたなら、今からご紹介する5つのパワースポットを押さえておきましょう。初めて櫛田神社へ訪れる方も、まずはチェックしてみてください。もちろん、最初に櫛田神社の神様にお参りするのをお忘れなく。
不老長寿の霊泉
お参りが終わったら、本殿のすぐ側に3羽の鶴飾りのある井戸があるので、そちらへ向かいましょう。この井戸は「霊泉鶴の井戸」と呼ばれ、不老長寿の言い伝えが残されています。 長生きができるとされるこの霊泉は、本殿地下の水脈から湧き出しています。
自分や家族、そして繋がりのある人々の不老長寿を祈願しながら、3回に分けて飲むのが良いとされています。 残念ながら、現在では飲むことが禁止されていますが、お水を手に受けながら不老長寿の願いを念じてみてはいかがでしょうか。
干支恵方盤
見逃す方も多いようですが、櫛田神社の楼門をくぐる際は忘れずに天井を見上げてみましょう。そこには、方角と干支の絵が描かれた丸い盤の「干支恵方盤」(えとえほうばん)が吊り下げられています。
毎年、大晦日になると新しい年の幸運な方角である恵方が矢印で示されるので、ぜひチェックしてみましょう。節分の定番である恵方巻も、この方角を向いて食べます。
また、全国的に見ても、櫛田神社の干支恵方盤はカラフルな色の珍しい造りです。ぜひ写真を撮って、家に帰ってからも恵方を意識しながら生活をしてみてはいかがでしょうか。何か幸運が舞い込むかもしれませんよ。
力石
本殿南側には、大きな石がずらりと並べられています。一つ約80㎏以上もあるこの大きな石たちは、「櫛田神社の力石」と呼ばれています。 昔はこの石を持ち上げて作物の豊作や天候を占っていましたが、次第に「こんな重い石を持ち上げられるぞ」と、力自慢をする道具へと意味合いが変化していきました。そこから、博多に住んでいる力士たちが力自慢で持ち上げた石を、櫛田神社に奉納する習慣が生まれています。
近年では、2012年に白鵬関が120㎏の力石を櫛田神社に奉納し、話題になりました。また、力石が置いてある場所には、「試石」との文字が刻まれた石がひとつだけ置いてあります。
この石はその名の通り、持ち上げられるかどうかを試すことができます。80㎏以上もある石を持ち上げられる力に自信のある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう。なお、他の石は触れることはできますが、持ち上げてもいいのはこの「試石」だけなので注意しましょう。
櫛田の夫婦銀杏
博多では、銀杏と書いて「ぎなん」と読みます。ここ櫛田神社の御神木である銀杏の木も、「櫛田のぎなん」として親しまれてきました。博多祝い唄にも「さても見事な櫛田のぎなん枝も栄ゆりゃ葉も繁る」と謡い囃され、縁起の良い木として慕われています。そんな「櫛田の銀杏」の樹齢は1,000年以上といわれ、延命長寿のシンボルともされています。
境内には「櫛田の銀杏」以外にも、縁結びや夫婦円満のご利益があるとされる御神木「夫婦銀杏(めおとぎなん)」があります。大樹3本の内の1本が雌木で、秋になるとたくさんの黄金色の実をつけることから、子宝のご利益もあるとされ霊樹として崇敬を集めています。
御朱印帳とお守り
櫛田神社では、「博多総鎮守」と書かれた御朱印を拝受できます。その他にも、山笠をイメージした色鮮やかな御朱印帳や、「博多仁和加(はかたにわか)」のお面が全面にデザインされたユニークでパッと目を引く御朱印帳も販売されています。櫛田神社でしか手に入らない御朱印帳は、お土産やご自分の旅の思い出にもなりおすすめです。 御朱印の他にも、櫛田神社を訪れたら手に入れていただきたいお守りがあります。それは、不老長寿や開運厄除け、商売繁盛など様々なご利益のお守りがある櫛田神社でも、特に人気の高い「身代御守」です。
御朱印の他にも、櫛田神社を訪れたら手に入れていただきたいお守りがあります。それは、不老長寿や開運厄除け、商売繁盛など様々なご利益のお守りがある櫛田神社でも、特に人気の高い「身代御守」です。
「身代御守」は、ひもを通して首から下げることもできる、木で作られたお守り。 病気や災いの身代わりとなってくれるようにと祈願されていて、山笠の参加者も同じように身代御守を首から下げています。私たちも日頃から持ち歩いておけば、神様に守られているようで安心できますね。
櫛田神社の祭り
節分大祭
毎年2月の節分の日にある櫛田宮のお祭りで、知名士による豆まきが行われます。これにあわせて、毎年1月下旬から2月10日頃までは、巨大なお多福の面が櫛田神社の山門前に飾られます。高さ、幅ともに約5mもあるお多福面の口の部分を通り抜けて参拝すれば、家内安全や商売繁盛のご利益があるそうです。
櫛田神社は757年に創建された古社ですが、この巨大お多福は近年の1961年に誕生しました。発案したのは、当時広告代理店に勤めていた田中諭吉氏。斬新でユーモアのセンスがあった田中氏は、節分大祭に参加しこの巨大お多福を思いついたのだそうです。
「福はうち」の言葉どおり、福は待つものとされてきましたが、待つばかりではなく自ら福を呼び寄せるという発想から、巨大お多福の口に自分から飛び込む参拝方法になったそうです。福をつかむには自ら動くと思えば、巨大お多福の口をくぐる時にかなり意識が変わるのではないでしょうか。
博多祇園山笠
7月に開催される祇園宮の奉納神事があります。それは、700年以上の伝統ある博多のお祭りとして有名な「博多祇園山笠」で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。博多祇園山笠は2週間にわたって行われ、櫛田神社はフィナーレを飾る「追い山」のスタート地点です。7月15日の追い山笠の「櫛田入り」は、勇壮なお祭りのクライマックスになります。
櫛田神社では、博多祇園山笠の期間中はお祭りに来られなかった方のために、境内に「飾り山笠」が飾られています。山笠は追い山の終了後に解体されますが、櫛田神社の飾り山笠だけは常設展示されます。博多祇園山笠の迫力や熱気をいつでも感じることができるため、周囲では記念撮影をする人も多く見られます。
博多おくんち
10月下旬に秋の豊穣に感謝するお祭りです。牛車にひかれる神輿行列や、稚児行列、ブラスバンドなどが豪華絢爛な祭りに彩りを添える御神輿パレードは、秋の博多の風物詩になっています。このように博多を代表するお祭りが季節ごとにあり、その中心である櫛田神社は、博多の人々にとっては生活に溶け込んだ身近で親しみのあるかけがえのない神社なのです。
櫛田神社の見どころ
博多歴史館
櫛田神社が所有する数多い社宝の中でも、歴史的に民族資料として価値の高いものばかりを厳選して展示。また、1818年(文政元年)に日本で最初の図書館である「櫛田文庫」が櫛田神社に開かれたことから、当時の貴重な書物も保管されています。
開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)、毎週月曜日休館、入館料:300円
博多備荒米の碑
博多は昔から町民自治が発達していました。1778年(安永年間)、天変地異などの非常災害に備えて、博多の有志による用心米の制度「博多義倉」と呼ばれるものがありました。博多備荒米の碑は、その名残として建てられたものです。
博多風神雷神
拝殿の破風に、風神雷神の木彫りが左右に掲げられています。よく見ると「一緒に暴風を博多で起こそう」と雷神から誘われた風神があっかんべぇをして逃げる様子が描かれています。これには、博多っ子のユーモアあふれる気質が表れているといえるでしょう。またこの風神雷神は、博多座に展示されているタペストリーのデザインにも使用されています。
博多べい
太閤豊臣秀吉の博多町割りにより復興した市街には、焼け石や焼け瓦など、大量の瓦礫が厚く塗り込められた「博多ベい」と呼ばれる土塀が連なりました。櫛田神社にある「博多べい」は、博多三傑の一人である嶋井宗室の屋敷に、約380年の風雪に耐えた最後の「博多ベい」として移築再建されました。

櫛田神社の特にパワーがあるスポット
やはり、御祭神が祀られている中殿、右殿、左殿です。中殿の大幡主命は開運や発展を司る神とされており、右殿の須佐之男命は災いを絶ち、左殿の天照大御神は万能の神として知られています。
博多総鎮守たる櫛田神社にて、ぜひ不老長寿や商売繁盛のご利益をいただいてくださいね。
まとめ
魅力満載の櫛田神社は、福岡観光では外せないスポットの1つです。櫛田神社を参拝することで、日本の伝統文化の素晴らしさを改めて実感してはいかがでしょう。もちろん、櫛田神社は博多のパワースポットとしても有名です。
主に、商売繁盛や不老長寿のご利益があるとされている櫛田神社。その他にも、境内には恋愛成就や夫婦円満のシンボルであるご神木や、霊泉鶴の井戸などがあり、パワースポット巡りの好きな方にもおすすめです。 中洲など博多の王道観光スポットからの距離が近く、博多駅からのアクセスも良好なので、気軽に訪れることができるのもうれしいですね。
ライターネーム/サクヤ凛
基本情報
住所:福岡市博多区上川端町1-41
電話番号:092-291-2951
公式HP:hakatanomiryoku.com
アクセス:地下鉄「祇園駅」2番出口 徒歩5分
料金:博多歴史館:入館料300円
※最新の情報は公式ホームページでご確認ください。
※記載した金額等は2022年11月時点のものであり、変更の可能性があります。