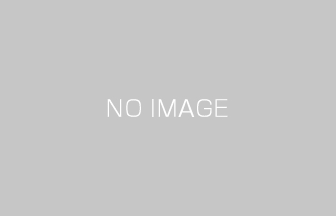住吉三神の荒魂を祀りパワー強力な長門国一宮 住吉神社
住吉三神の荒魂を祀りパワー強力な長門国一宮 住吉神社
山口県下関市に鎮座する長門国一宮 住吉神社は、長門国一宮で「日本三大住吉」の1つに数えられるパワースポットです。山口県でも最強クラスのパワースポットといわれる長門国一宮 住吉神社とは一体どんな神社なのでしょうか?今回は、そんな「長門国一宮 住吉神社」の人気の秘密や歴史、ご祭神、ご利益、見どころ等、ポイントごとに紹介していきます。
長門国一宮 住吉神社はどんな神社?特徴は?
長門国一宮 住吉神社は、大阪市の住吉神社、福岡市の住吉神社とともに「日本三大住吉」に数えられ、長門国一宮として知られる日本有数のパワースポットです。JR・山陽本線の新下関駅からタクシーで5分程のアクセスしやすい場所に鎮座しています。神社本庁の別表神社に列格しており、境内は広く、社叢は楠やヤマビワ、コジイなどが原生しており、山口県の天然記念物に指定されています。
本殿は国宝に、拝殿は国の重要文化財に指定されていて、そのほかにも銅鐘などの工芸品や楼門等、神社の所蔵品の多くが国の重要文化財や登録有形文化財、市の指定文化財に指定されています。大阪の住吉大社が住吉三神の和魂を祀るのに対し、山口の住吉神社は、住吉三神の荒魂を祀っているようです。
長門国一宮 住吉神社の例大祭は「御斎祭(おいみさい)」といわれる神事で、毎年12月8日から15日の8日間催され、境内に注連縄を張り巡らし、一般参拝ができないようにし、神職も境内の外へ出ないという厳重な特殊神事となっています。
長門国一宮 住吉神社の歴史
長門国一宮 住吉神社の創建は古く、神功皇后の三韓征伐の際、新羅に向かう神功皇后の前に住吉三神が現れ、お告げ(神託)を受け取り、航海を守護。その帰途に再び住吉三神が現れ、「我が荒魂を穴門(長門)の山田邑に祀れ」とのお告げの通りにその地に祠を建てたのが起源となっています。
軍事と海上交通の神として厚い崇敬を受け、鎌倉時代には、源頼朝をはじめ、歴代将軍から社領の寄進を受けています。その後は大内氏や毛利氏から崇敬され、江戸時代には、毛利氏によって社殿の修復が成されます。
本殿は室町時代の1370年に造営されたもので1953年に国宝に指定されました。拝殿は1539年に毛利元就の寄進によって造営され、こちらは1954年(昭和29年)に国の重要文化財に指定されています。明治維新後、1871年(明治4年)に国幣中社に列格し、1911年(明治44年)には官幣中社に昇格しました。

長門国一宮 住吉神社のご祭神
長門国一宮 住吉神社のご祭神は住吉三神、応神天皇、武内宿禰命、神功皇后、建御名方命の7柱です。
住吉三神(表筒男命・中筒男命・底筒男命)
住吉三神は全国の「住吉神社」などに祀られている三神で、表筒男命(うわつつのおのみこと)・中筒男命(なかつつのおのみこと)・底筒男命(そこつつのおのみこと)の三柱を指します。この三神は、伊邪那岐命の「禊」で生まれた海の神です。住吉三神は、航海安全、禊祓(みそぎはらえ)、漁業守護、和歌上達などのご利益を司っています。
応神天皇(おうじんてんのう)
応神天皇は第15代の日本の天皇で、4世紀後半頃の大王といわれており、仲哀天皇と神功皇后の間に生まれた第4皇子です。古事記と日本書紀には、大陸から日本に渡ってきた渡来人を用いて国を発展させ、中世以降は軍神八幡神としても信奉されました。
武内宿禰命(たけしうちのすくねのみこと)
景行(けいこう)天皇・成務(せいむ)天皇・仲哀(ちゅうあい)天皇・応神天皇・仁徳(にんとく)天皇の5代の各天皇に仕えたといわれる伝説上の人物で、蘇我氏など中央有力豪族の祖ともされています。かなり長寿の神様として、長寿の神や武運長久の神、宰相の神の神格を持ち、延命長寿、武運長久、厄除け、立身出世などのご利益があります。
神功皇后(じんぐうこうごう)
神功皇后は仲哀天皇の没後、新羅に出兵して三韓征伐を果たし、仲哀天皇の意志を継いで熊襲討伐を成し遂げるなど、天性の統治能力のある女帝と記されています。危険な状況の中で無事、応神天皇を出産し、立派に育て上げたことから、武運長久のみならず、安産や子育てのご利益もあるといわれています。
建御名方命(たけみなかたのみこと)
大国主神の御子神であり、国譲りに反対して建御雷神(たけみかづちのかみ)との力比べに敗れたとされる建御名方神が第5殿の御祭神として祀られています。建御名方神の神格は、「軍神、狩猟神、農耕神、蛇神(龍神)、水神、風神」で、「勝利祈願、武運長久、商売繁盛、五穀豊穣、子授かり、子孫繁栄」といった多岐に亘るご利益を司っています。

長門国一宮 住吉神社のご利益とは?
長門国一宮 住吉神社の主なご利益は勝運、交通安全、海上安全、厄払い、商売繁盛、五穀豊穣、家内安全、学力向上、病気平癒などが挙げられます。
長門国一宮 住吉神社の見どころとは?
次は長門国一宮 住吉神社の見どころについて見ていきましょう。長門国一宮 住吉神社の見どころについては以下の通りです。
国宝の本殿
5つの社殿が相の間でつながっており、柱間が9つの「九間社(きゅうけんしゃ)流造」の本殿は、室町時代の1370年に建立され、全国でも珍しい造りの建造物として国宝に指定されています。正面の5か所には千鳥破風という小さな屋根が付いています。歴史ある美しい日本建築は見ごたえ十分です。
国の指定重要文化財・拝殿
檜皮葺きの拝殿は、戦国時代の1539年、毛利元就の寄進により造営されたものです。拝殿は国の重要文化財に指定されています。細部手法に創建時の特徴が見られます。縦長に配置する例は少なく、貴重な文化財です。朱塗りのご社殿が美しく、拝殿の扁額には、「住吉荒魂本宮」と記されています。長門国一宮 住吉神社では、住吉三神の荒魂が祀られているようです。
神池のカモ
長門国一宮 住吉神社では、2020年に神池にカモを6羽迎えており、人馴れした可愛らしいアイガモ達に会えますよ。無邪気に泳いだり、日向ぼっこする鴨にも癒やされますが、鯉や亀にも癒やされます。

ご神木の大楠
長門国一宮 住吉神社の境内(稲荷社近く)にはご神木の巨大な楠があり、ご祭神の武内宿禰命手植えの大楠といわれています。根周りは60m余にも及ぶ大木で、非常に強いエネルギーが感じられるスポットです。

随神門(楼門)
入母屋造檜皮葺の楼門は朱塗りの立派な門で、現在のものは1901年(明治34年)に再建されたもの。随神門の両側に配置されている随身像は色鮮やかで、古さを感じさせませんが、鎌倉時代に作られたものだそうです。1つ1つが美しく、一見の価値があります。

長門国一宮 住吉神社のお守り・御朱印帳
せっかく神社の参拝に訪れたなら、お守りや御朱印はチェックしておきたいですね。次は、長門国一宮 住吉神社で販売されている「お守り」「御朱印帳」について見ていきましょう。
お守り
長門国一宮 住吉神社のお守り情報はありません。初詣の時などは頒布されているようです。
御朱印帳
長門国一宮 住吉神社のオリジナル御朱印帳は、濃紺を基調とした色味で、表紙に「住吉荒魂本宮」と記されており、表紙には拝殿が、裏表紙にはご神木の大楠がデザインされています。通常の御朱印は2種類、季節限定の御朱印があります。手書きでもいただけるようです。

長門国一宮 住吉神社で特にパワーがある場所は?
長門国一宮 住吉神社で特にパワーがある場所は、住吉三神の荒魂が祀られているといわれる本殿です。「荒魂」は非常に強いパワーを持っているといわれており、願いも叶いやすいといわれています。

まとめ
「日本三大住吉」のうちの1つで、長門国一宮である住吉神社。ご利益は勝運や海上安全を含め多岐に亘り、住吉三神の荒魂を祀ってある為、パワーも強力で、願いを叶える力も強いといわれています。ご神木の楠も非常にパワーが強い場所なので、是非立ち寄ってみて下さいね。12月の例大祭期間のみ一般参拝ができない為、その期間以外なら大丈夫です。
ライターネーム Kikumikan
基本情報
住所:山口県下関市一の宮住吉1丁目11-1
電話番号:083-256-2656
拝観時間:6:00~18:00(冬季は~17:30)
定休日:12/8~12/15(例大祭期間のみ一般参拝休止)
HP:https://www.facebook.com/aramitamahongu/
駐車場:無料駐車場あり(300台程度)
アクセス:
・JR山陽新幹線・山陽本線 新下関駅から徒歩約20分(タクシーで約5分)
・サンデン交通バス「一の宮」バス停から徒歩約10分
・中国自動車道 下関I.Cから車で約6分